2025/11/18 書籍レポート:『考察する若者たち』― なぜ今、「正解」が求められるのか?
こんにちは! Phoenix-Aichiオンライン教室、広報担当の夏目です。
最近、YouTubeやSNSで「伏線回収」「裏設定の解説」「真犯人はコイツだ!」といった動画や記事をよく見かけませんか? ドラマ『あなたの番です』や、小説・映画『変な家』のように、制作者側が意図的に「さあ、謎を解いてみてください」と仕掛けてくる作品も大ヒットしています。
なぜ今、これほどまでに「考察」がブームになっているのでしょうか?
この鋭い問いに迫った一冊が、今回ご紹介する三宅香帆さん著『考察する若者たち なぜ令和の若者は「正解」を欲しがるのか?』です。本書は、「ただ面白い」だけでは満足できず、そこに「プラスアルファの意味」を求めてしまう現代人の心理と、その背景にある「痛み」を鮮やかに解き明かしています。
これは若者だけの話ではありません。情報の洪水の中で、確かな「芯」となるものを探したい私たち全員に関わるお話です。一緒にその理由を探っていきましょう!
「批評」の時代は終わり、「考察」の時代が来た
まず、本書が定義する現代の「考察」とは何でしょうか?
それは、「事件の真犯人などの『謎』を、作中のヒントから推察し、その推察をSNSやブログで語ること」を指します。重要なのは、ミステリー以外の作品、例えば『鬼滅の刃』や『ONE PIECE』のような作品に対しても、「作者は謎を仕掛けているはずだ」という前提で、読者や視聴者が「伏線」や「裏設定」を探し出すこと。これが現代のスタンダードな楽しみ方になりつつある、と著者は指摘します。
「考察」と「批評」の決定的な違い
かつて、作品の楽しみ方といえば「批評」が主流でした。では、「考察」と「批評」は何が違うのでしょうか?
- 批評: 「作者すら思いついていない作品の解釈を提示する」こと。解釈は無限にあり、「正解」はありません。読む人それぞれの自由な解釈が主役です。
- 考察: 「作者の意図」を強く意識します。作者が仕掛けた「謎」があり、それに対する「一つだけの正解」が存在すると信じられています。
例えば、スタジオジブリの映画『君たちはどう生きるか』。この作品をめぐり、NHKの番組が「宮崎駿監督が高畑勲監督の死を乗り越えるために作った」という「ジブリからの回答」らしきものを放送しました。多くの人は、これを見て「制作者の“答え”を知った」と安心したかもしれません。
しかし、作品には主人公の少年の複雑な葛藤も描かれており、単純に「二人の監督の関係性」だけで割り切るのは難しいはずです。こうした割り切れない「複雑さ」は、かつての「批評」の格好のテーマでした。しかし、「考察の時代」において、こうした複雑さは好まれません。
「考察には『正解』がある」一方で、「批評には『正解』がない」。
なぜ「正解」が求められるのでしょうか?
著者は、「正解がないなら、批評の努力は報われない」と感じる心理があるからだと言います。自分独自の感想を深めるよりも、みんなで探し当てられる「報われるゴール」(=正解)に至るプロセスを選ぶ。現代では、余暇や楽しみにおいてさえ、「報われポイント」が求められているのです。この「考察文化」は、作品の受容体験そのものを「正解のあるゲーム」に変えてしまった、と言えるでしょう。
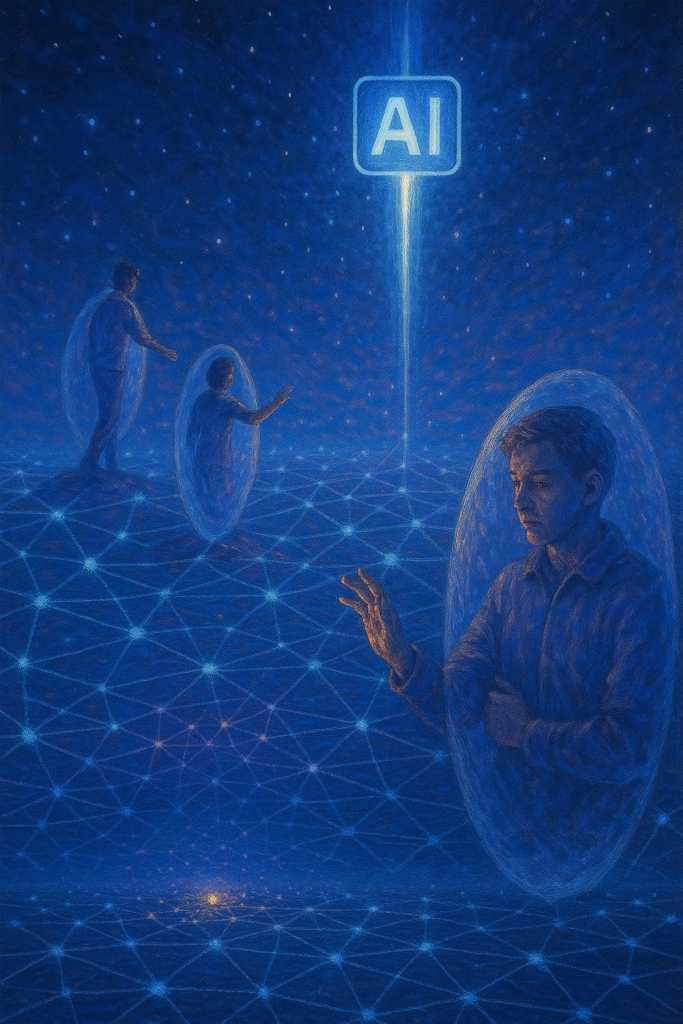
アルゴリズムが作る「界隈」と、安心できる「擬似親」
私たちが「正解」を求めるようになった背景には、インターネット環境、特に「アルゴリズム」の存在が大きく関わっています。
💡 専門用語解説:レコメンド・アルゴリズム
これは、YouTubeやTikTok、Amazonなどが「あなたへのおすすめ」を表示する仕組みのことです。私たちが過去に見た動画、クリックした商品、検索したキーワードなどのデータを分析し、「あなたが好きそうなもの」を自動で判断して提示してくれます。
このアルゴリズムは非常に便利ですが、同時に「『正解』という名の最大公約数を強化させる表現を支持する傾向」があると著者は指摘します。つまり、多くの人が「良い」と反応するものが、さらに多くの人におすすめされる、という循環が生まれるのです。
その結果、私たちは自分の個別な好みを探すよりも、アルゴリズムがおすすめする「みんなが良いと言うもの」を受け入れやすくなります。こうして、「同じような主張を持つ人たちの集団」が形成されます。これが、最近よく聞く「界隈(かいわい)」という言葉です。
「界隈」の中の人間関係
「界隈」は、特定のジャンル(例:特定のゲーム、アイドル、趣味など)を好む人たちの集まりです。アルゴリズムは、一度ある界隈に属すると判断されたユーザーに、その界隈でウケるコンテンツをどんどん提供します。私たちはその「おすすめ」の範囲内で満足し、わざわざ界隈を飛び越えて新しいものを探す冒険をしなくなります。
この「界隈」は、人間関係にも影響を与えています。
NHKの調査によると、「悩み事を相談する相手」として「友だち」を選ぶ中高生が激減しているそうです。
- 1982年:「友だち」が 74.2%
- 2022年:「友だち」が 40.6%
代わりに増えたのが「お母さん」でした。
- 1982年:「お母さん」が 18.0%
- 2022年:「お母さん」が 30.2%
※注:PDFの要約では1982年「友だち」74.2%→2022年「4.6%」とありますが、これは元のNHK調査データ(2022年調査)の「友だち(学校の)」40.6%と「友だち(学校以外の)」4.6%の取り違えの可能性があります。ここでは文脈の自然さを優先し、より大きな傾向(友人への相談減少、母親への相談増加)を示す形で記述を調整しています。いずれにせよ、傾向は同じです。
なぜ、友達に相談しなくなったのでしょうか? それは、「界隈」という友情関係が、「共感できる価値だけを共有する場」になっているからかもしれません。意見が対立しそうな面倒な悩みは、界隈の調和を乱すノイズとして敬遠されます。
その一方で、「親」は(多くの場合)自分で選べない、絶対的な関係です。そこには「界隈」のようなフラットさとは違う、「正しさ」のヒエラルキー(上下関係)が存在します。
著者は、ヤマシタトモコさんの漫画『違国日記』を例に挙げます。この作品では、両親を亡くした主人公が、自分とは全く「界隈」の違う叔母と「親子」として暮らすことになります。主人公は、界隈の友達には言えない悩みも、この「擬似親(ぎじおや)」である叔母には打ち明けられるようになります。
これは、アルゴリズムによってフラット化し、「正しさ」がバラバラになった現代社会で、「『正解』に近いことを教えてくれる理想的な相談相手」=「擬似親」というファンタジーを、私たちが求めていることの表れではないか、と本書は分析します。
「ググる」から「ジピる」へ ― AIは“完璧な擬似親”か?
「報われたい」「正解が欲しい」という私たちの欲求に応える、最強の存在が登場しました。それが、AI(人工知能)です。
最近では、ChatGPTを使うことを俗に「ジピる」と言うそうです(「ググる」のGPT版ですね)。この二つには、決定的な違いがあります。
- ググる(Google検索): 年代も作者もバラバラな情報が大量にヒットします。私たちはその「情報の渦」の中から、どれが信頼できるか、どれが自分に必要かを「選び取る」必要がありました。
- ジピる(ChatGPT): ChatGPTという「大きな個体」が、一つの「正しい答え」を提示してくれます。私たちはもう、複雑な選択をする必要がありません。
「問いに対して必ず正しい(らしき)答えが返ってくる」という体験は、「報われ度」が非常に高いものです。この点で、AIは「作者による唯一の正解」を好む「考察」文化と非常に親和性が高いと言えます。
AIは、まさに私たちが求めていた「正解を提示する擬似親」として、今後ますます受け入れられていくでしょう。論理的で、感情的にならず、親よりも話しやすい相談相手として。
AIが作る「繭(コクーン)」
しかし、ここには大きな落とし穴があります。歴史家のユヴァル・ノア・ハラリは、AI社会の危険性を警告しています。
Googleが情報の「網(ウェブ)」として世界を開いてきたのに対し、ChatGPTのようなAIは、私たちを情報の「繭(コクーン)」の中に閉じ込めてしまうのではないか、というのです。
AIが提示する「正解」は、国や文化圏ごとに最適化された倫理観に基づいています。私たちは、AIという「擬似親」がくれる「正しさ」に満足し、それが偏ったものであることに気づけなくなるかもしれません。
陰謀論も混ざる情報の濁流の中で、頑張っても報われないことが多い現代。だからこそ、少しでも「正解」らしさのあるAIや、「報われるゴール」としての「考察」にしがみつきたくなる…。その気持ちは痛いほどわかります。しかし、その「正しさ」にしがみつくことで、私たちは本当に報われているのでしょうか?
「自分らしさ」が「生きづらさ」になる時代
最後に、本書は「自分らしさ」というテーマに切り込みます。
💡 専門用語解説:アテンション・エコノミー
「注目」そのものに経済的な価値がある、という考え方です。現代のインターネット社会では、いかに人々の注目(アテンション)を集め、滞在時間を増やすかがビジネスの鍵となります。そのため、内容の質よりも「いかに強く反応されるか(バズるか)」が重視されがちです。
このアテンション・エコノミーとアルゴリズムの社会では、「超有名作家」といった権威(固有名詞)の価値は下がっていきます。再生数や「いいね」の数といった数値だけで、大物芸能人も名も知らぬ若者もフラットに比べられます。
これは「考察」文化にも通じます。「考察」において重要なのは「謎が解けるか」であり、「語り手の個性は必要ない」のです。
「最適化」される私たち
アルゴリズムは、私たちに「おすすめ(レコメンド)」と「個人化(パーソナライズ)」を自動(オート)で提供してくれます。私たちが「選ぶ」という主体的な行為は、もはや必要ありません。
どんな作品をよいと感じているかといった「『自分らしさ』がどうでもよくなった」のだ。
この流れは、私たちの人間関係にも及んでいます。その場の空気を読んで「キャラ」を「最適化」させることが求められます。「自分らしさ」を貫くことは、むしろ「世界に最適化できていない」ことの証であり、「自分らしさとは、生きづらさになっている」と著者は断言します。
必要なのは、オンリーワンの独自性ではなく、その「界隈」ごとに最適化された「自分」なのです。
最近流行しているMBTIなどの性格診断は、まさにこの流れを象徴しています。「あなたはISTP(巨匠タイプ)です」といった16タイプの「ラベリング」は、「オンリーワンの自分」を苦労して探すよりも、ずっと手軽に「報われ」ます。
私たちは「オンリーワンの自分より、ラベリングされた自分でありたい」という風潮に、うっすらと取り巻かれているのです。
【広報担当・夏目の熱血感想文】私たちは「繭」の中で何を見るか
いやあ、凄まじい本でした。広報担当の夏目です。正直、読みながら何度も胸が苦しくなりました。なぜなら、本書で語られる「痛み」や「弱さ」は、まぎれもなく私自身の中にもあるものだったからです。
「報われたい」。このシンプルな欲望が、私たちの文化や人間関係、さらには「自分」という概念そのものまで変容させている。このダイナミックな分析には、ただただ圧倒されました。
私たちは皆、情報の濁流に流されまいと、必死に「正解」という名の流木にしがみついているのかもしれません。AIという「擬似親」が差し伸べてくれる手が、どれほど魅力的に映ることか。
「ジピれば」答えが出る。「考察動画」を見れば「裏設定」がわかる。MBTI診断をすれば「自分のタイプ」がわかる。なんと楽なことでしょう。そこには、かつて「批評」や「自分探し」に伴った、面倒で、報われないかもしれない「努力」は必要ありません。
しかし、本書は最後に問いかけます。その「正しさ」にしがみつくことで、私たちは本当に報われているのだろうか、と。
アルゴリズムが自動で最適化してくれた「繭(コクーン)」の中は、とても快適でしょう。共感できる「界隈」の仲間に囲まれ、AIという「擬似親」が「正解」を教えてくれる。そこには「生きづらさ」の原因となる「自分らしさ」など、もはや必要ありません。
でも、本当にそれでいいのでしょうか。
著者の三宅さんは、この「最適化」の流れを否定しません。その上で、終章では、それでもなお「私らしさ」を取り戻すための選択肢を提示してくれています。(ここはぜひ、本書を手に取って読んでみてください!)
「考察」のゲームを楽しむのも自由。でも、時には立ち止まって、「正解」のない「批評」の世界に足を踏み入れてみる。作者の意図(=正解)を探すだけでなく、「私はどう感じたか」という、誰にも最適化されない、面倒で、報われないかもしれない「自分だけの感情」と向き合ってみる。
Phoenix-Aichiオンライン教室で私たちが大切にしている「学び」も、本質はそこにあるのかもしれません。AIが提示する「正解」を覚えることではなく、情報を選び、考え、自分なりの「解釈」を生み出すプロセスそのものを楽しむこと。
この本は、快適な「繭」の中でまどろむ私たちに、「本当にそれで満足なのか?」と、冷水を浴びせかけながらも、そっと毛布をかけてくれるような、厳しくも愛のある一冊でした。超おすすめです!

